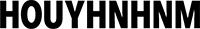Girls Just Want To Have Fun!

Mike Mills and 20th Century Women.
マイク・ミルズの回顧録。
Photo_Satomi Yamauchi
Interview & Text_Yasuo Murao
Interview & Text_Yasuo Murao
JAPANESE
ENGLISH
グラフィックデザインやアートといった幅広い分野で活動するマイク・ミルズが、
最近では映画監督としての活躍も目立つなかで、
自伝色の濃い物語『20センチュリー・ウーマン』を完成させた。
シングルマザーのドロシアと暮らす15歳の息子ジェイミーは、
年上のカメラマンのアビーや幼なじみのジュリーとの交流を通じて成長していく。
パンク、スケボー、フェミニズム、そして個性的な女性たち。
青春期に影響を受けたものを綴った本作の話を中心に、クリエイターになるまでの日々をマイクに聞いた。

自分の知っている女性たちから生まれた物語。
- 前作『人生はビギナーズ』は父親についての物語でしたが、今回は母親を中心にした女性たちの物語ですね。
- マイク・ミルズ:父親の物語を作ったんだから、次は母親を題材にしてもいいんじゃないかと思ってね。ぼくの母親はちょっと変わっていて、すごくタフで、フェミニストの女性だった。そして、姉のメグはNYで勉強していたけど子宮頸癌になってしまった。そんな風に自分の知っている女性たちのことを思い浮かべているうちに、頭のなかで女性たちの小さな宇宙ができてきて、そこからストーリーを生み出していったんだ。
- お姉さんのバックグラウンドはアビーに反映されているんですね。グレタはジェイミーにパンクの魅力を教えますが、今回の映画のなかでパンクは重要な役割を果たしているように思います。
- マイク・ミルズ:ぼくの人生においてパンクに出会ったことはすごく大きな意味を持っていて、パンクを通じて「自分は何者なのか?」というのを初めて見つけることができたんだ。それまでメインストリームのカルチャーのなかでは自分の居場所を見つけることができなかった。だから、今回の映画においてパンクはもう一人の登場人物ともいえるね。
- アビーがジェイミーとザ・レインコーツの『Fairytale In The Supermarket』のレコードを部屋で聴くシーンが印象的でした。アビーはジェイミーにフェミニズムも教えますが、パンクは女性たちに活動の場を与えたシーンでもありますよね。
- マイク・ミルズ:確かにパンク・シーンは、女性たちに初めて演奏する場所を与えたんだと思う。でも、スリッツやスージー・スーに話を聞いたら「パンクは女性蔑視の世界だった」と言うと思うけどね(笑)
- 確かにマッチョなシーンですからね。映画ではパンク・シーンのなかにも棲み分けがあって、ハードコア・パンクを聴いている者はアート系のパンクをバカにしています。トーキング・ヘッズが好きなジェイミーが、ハードコア・パンクが好きな友達とケンカになり、家の車に“ART FAG(アートかぶれのオタク野郎)”と落書きされますが、あれは実際にあったことなんですか。
- マイク・ミルズ:通っていたハイスクールの近くにパンクスが住んでいるパンクハウスがあって、そこに“ART FAG”って落書きがしてあったんだ。ハードコアの人たちにとっては、ジョイ・ディヴィジョンもバウハウスもワイアーも、ギャング・オブ・フォーだって“ART FAG“だったんだ。そんなふうに、当時はパンク・シーンのなかでも分かれていた。映画ではそこもきっちり描きたかったんだ。
- あのシーンの後、ドロシアがジェイミーのことを理解するために、実際にトーキング・ヘッズを聴いてみるシーンが素敵でした。
- マイク・ミルズ:あれは実際にあったことではないけど、母はぼくがやっていたパンク・バンドのライヴを観に来てくれたよ。そして、あとで歌詞についていろいろ感想を言ってくれたりした(笑)。息子が関心を示すものを自分なりに理解しようとする母親だったんだ。そういうところはクールだったと思う。
- 映画のサントラにはトーキング・ヘッズの曲が2曲使われていますが、あなたにとって特別なバンドなのでしょうか。
- マイク・ミルズ:うん。トーキング・ヘッズってパンクだけどクリエイティヴで、しかも自由で。マッチョ感のないパンクのいい例だと思う。ファースト・アルバムの『1977』から4作目の『Remain in Light』まで、アルバムを出すごとにサウンドが発展していく。それって勇気もあるし、すごいことだと思うよ。いまだに彼らのサウンドからはインスピレーションを受けているんだ。
- トーキング・ヘッズはアートに対しても先鋭的なバンドでしたよね。かつてNYで写真を勉強していたアビーは、ジェイミーに街を出て行くように忠告しますが、あなたが住んでいたサンタバーバラはアートには無縁の街だったのでしょうか。
- マイク・ミルズ:サンタバーバラは郊外にある裕福なエリアで、すごく退屈なんだ。アビーが街を出るように忠告するのは、「街にいたら変人であることの利点がなくなって、普通の人になっちゃうよ」ということ。気がついたら、地元のサングラスショップで働くことになってしまう。

グラフィック・アーティストは3番目の選択肢だった。
- あなた自身、サンタバーバラを出てNYに進学したことは人生のターニングポイントでしたか?
- マイク・ミルズ:すごく大きな出来事だったよ! 84年にニューヨークに出てきたんだけど、火星にでも行ったような感じだった(笑)
- 何に驚きました?
- マイク・ミルズ:まず、人がすごく多かった。しかも、様々な人がいる。サンタバーバラは白人ばかりだけど、ニューヨークはいろんな人種がいた。あと、すごくラフというか。サンタバーバラはのんびりしているからね。
- NYではグラフィックを学んだそうですが、バンドを続けて音楽の道を進もうとは思わなかったんですか。
- マイク・ミルズ:それは考えたけどダメだった、演奏がヘタだったからね(笑)。実は最初の夢はスケートボードの選手だったんだ。でも、ダメだった。その次がパンク・バンドだったんだけど、それもダメで。じゃあ……っていうことで、グラフィック・アーティストを目指すことになったんだ。
- グラフィックは3番目の夢だったんですね。
- マイク・ミルズ:そう(笑)。絵は昔から描けたから、NYのアートスクールに行ったんだ。でも、アートスクールを卒業した頃はソーホーにすごく活気が出てきて、アートは金持ちのためのオシャレなオブジェみたいになっていたんだ。ぼくは資本主義への反抗のつもりでアートを始めたのに、気がついたら資本主義の一部に巻き込まれたような状態になってしまっていた。それで「これじゃダメだ」と思って、アートではなくデザインをやるようになったんだ。あと、アートが排他的で限られた人だけのものになってしまっていたのも嫌だった。そうじゃなくて、多くの人に見てもらえる、もっと娯楽性のあるものをやりたかったんだ。
- デザインを手掛けるうえで、10代の頃に聴いていたレコードのアートワークから影響を受けましたか?
- マイク・ミルズ:もちろん。パンクはいまのヒップホップと同じですべてに美的センスがあったからね。
- ちなみに、お気に入りのジャケットを教えてもらえますか。
- マイク・ミルズ:ジャームズのファースト。ダムドのアルバム全部。セックス・ピストルズの『Never Mind the Bollocks』は当時すごくカッコいいと思ったけど、いま見るとありきたりな感じがするね。ワイアーの『Pink Flag』、これはすごく美しい。ジョイ・ディヴィジョンの『Unknown Pleasures』も良いね。そして、トーキング・ヘッズは全部好き。いま見ても素晴らしい。
- 現在あなたはジャケットのデザインも手掛けていますが、デザインをする時に心掛けていることはありますか。
- マイク・ミルズ:レコードデザインに関して言うと、折衷的というのかな。なんでもありというか、あえて“自分“というアイデンティティーを持たないようにしている。「これぞマイク・ミルズ」という作風を持たず、そういうものを壊すことを心掛けたから、ジャケットごとに作風は違うんだ。いい意味で精神分裂的というか。
- X-girlのデザインを手掛けていたこともありましたが、ブランドのイメージを作るという仕事はやってみていかがでした?
- マイク・ミルズ:あの時は、まずキム(・ゴードン)とデイジー(・ヴァン・ファース)からテーマをもらっていた。具体的に何をしてほしいということではなく、コンセプチュアル・アート的な観点でね。ぼくはもともとそういう勉強していたから、仕事はやりやすかった。例えば“インターナショナル・コミュニケーション”というテーマを与えられて、何ができるかを考えて仕事をしていく。そこでは監督にもなれるしデザイナーにもなれるんだ。

- これまでいろんな仕事を手掛けてきたなかで、映画監督という仕事の醍醐味はどんなところでしょう。
- マイク・ミルズ:映画ってすごく大きなプロジェクトで、いろんな楽しさがある。脚本を書く楽しみもあるし、それ以上に撮影をしているのが楽しい。クルーや役者と一緒に作業をするのが好きだからね。編集も嫌いじゃない。編集から生まれる魔法みたいなものがあるからね。あと、公開した時に観客に見せる喜びというのもある。特にヒットしたときはうれしいよ(笑)。今回の映画は完成するまでに5年かかっているから、いろんなことがあったんだ。
- 最後に『20センチュリー・ウーマン』のヴィジュアルについて教えてください。色彩やデザインについて意識したことはありましたか。
- マイク・ミルズ:今回動きのあるエキサイティングな映画にしたかったんだ。だから、(フェデリコ・)フェリーニの映画のような、お祭りのような雰囲気にしようと思って、色はいままでよりも強めにした。セットの美術はもちろん、ネオンサインの色であるとか、アビーが履いているピンクのタイツとか。これまでの作品よりも大胆で幅のある色使いになっていると思う。それは1979年という時代にあっているし、そこから生まれるエネルギーを表現していると思うよ。