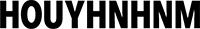Girls Just Want To Have Fun!

Keep stepping ahead.
前に進む力を与えてくれるDYGLの音楽。
Photo_Ko-ta Shouji
Interview & Text_Yukiko Inoue
Interview & Text_Yukiko Inoue
JAPANESE
ENGLISH
現在の音楽業界を賑わせているのは、間違いなく20代の若手たち。
その中でも、愚直にロック・サウンドを貫くことで一際強い存在感を放っているDYGLが、
ついに1stフルアルバム『Say Goodbye to Memory Den』をリリース。
あのアルバート・ハモンドJr.をも虜にするサウンドは、いかにして生まれたのか?
世界水準の注目を集める彼らの貴重なインタビュー。
“Day-Glo=安っぽくて派手“がバンドのスタンスになるかなって。
- みなさん明治学院大学の同級生ということですが、そもそもどういう経緯でバンドはスタートしたのでしょうか?
- Akiyama(Vo, G)初めは皆サークルが同じで、その定期演奏会用にDe Nadaという名前でぼくとKamotoとShimonakaの三人でバンドを組んだのがきっかけで。もともとはShimonakaとKamotoの二人がバンドを始めて、そこにぼくが誘われました。
- 編成はいまの通りですか?
- Akiyamaギター、ギター、ドラムをみんなで回す感じで。でも初めはぼくがドラム叩くことが多かったですね。
- Shimonakaドラムを叩いて歌っているのがAkiyamaで。
- すごいですね。
- Akiyamaかなりイレギュラーな編成でしたね。
- 当時からオリジナルの曲をやっていたのですか?
- Shimonaka基本的にはそうで、あとはほぼコピーみたいな感じ。Smith Westernsの『Weekend』という曲と…。
- AkiyamaWATERSの曲をやったりしていました。
- 結構最近の話ですね。
- Akiyamaそうですね。ロックの長い歴史で言えば。
- ShimonakaそのときはThe White Stripesにめっちゃ似ている曲をやったり、あとオーストラリアにPaint Fumesという超インディなガレージバンドがいて、彼らはギター2人とドラムだけで編成が同じだったと思うんですけど、こういう感じなら多分ぼくらにもできると思って。そういうバンドの音楽をやったりしていました。
- そこに途中からKachiくんが加入したという?
- Shimonakaその前にぼくの幼馴染が一時期ベースを弾いていたんですけど。その彼はバイトと学業に専念しなければならない状況になっちゃって。
- Akiyamaとにかく3人の編成に限界が見えはじめて。音楽的にももっと広くやりたいという感覚が自分たちのなかで芽生えたのが分かったので、ベーシストが欲しいという話になりました。それでYkiki Beatで既に一緒にやっていたKachiに、DYGLでも一緒にやってくれないかなという話になり。

- DYGLというバンド名について教えていただけますか?
- Akiyama“Day-Glo”という単語は実際に存在しているんです。蛍光色という意味なんですけど、その単語の別の説明に「安っぽくて派手」というスラング的な意味もあるらしく、それが自分たちとしては「バンドのスタンスにもなるから面白いね」という話になりました。
- サークルのバンドだったということですが、その先にビジョンは持っていましたか?
- Shimonakaいや、全くなかったですね。
- Akiyamaそのとき楽しいことをやっているという。
- Shimonakaそれでも、スタジオに入った時間とか曲が出来ていく時間は、「めちゃめちゃいい感じなんじゃないかな」というのはあったんですけど。でも、先のビジョンなんて全然ありませんでした。
- Shimonakaくん以外のメンバーは同時並行でYkiki Beatもやられていたわけですが、2つのバンドを学生生活のなかでやるのは大変だったのでは?
- Kachiぼくがいた時期は大学の終わりの方で、授業も全然なかったんでそこは問題なかったですね。
- 先にYkiki Beatが世間的に知られることになったわけですが、結果DYGLがプロとしての道を正式に歩みだしているわけで。その経緯についても聞かせていただけますか?
- Akiyamaどちらのバンドもそれぞれのコンセプトがあったので、別のものとしてきちんと成立するなら両方続けたいと思っていました。でも、実際には音楽的な嗜好や創作に対するそれぞれの姿勢をひとつのものにするというのは理屈で片付けられるものでもなく、やっている感覚としてみんながクリエイティブになれるバンドではなくなっているのを感じて。DYGLでの活動がYkiki Beatの休止の理由に関係したわけではなかったですね。物理的にそれぞれのバンドの活動が影響することはもちろんありましたが、それは予定が被るなどの悪い面だけでなく、お互いの活動の幅を広げ合うという良い面もありましたし。
- 自然な流れのなかでこの結論に至ったと。
- Kachiそうですね。どっちのバンドのせいでというわけではなく、あくまでひとつのバンドとしてそういう結果になったという。

- 前作も海外で録音されてますし、最近はSXSWにも出演されたりとワールドワイドなスタンスで活動されているようにお見受けします。英語で歌うのは日本のメインストリームでもいまでは珍しくないですが、個人的には同世代のワイワイしているバンドと少し距離を置いてるようにも見えます。その辺りはいかがですか?
- Akiyamaそうですね。自分たちと共感できる姿勢で音楽をやっている人と出会うことは少ないです。それは別に英詞云々の問題では無いんですけど。英詞でそれっぽいことをやっているバンドより、日本語詞でもmitsumeのようなバンドと話が合うこともありますし、肝心なのは創作への向き合い方だと思います。音楽をアクセサリーにし過ぎているバンドはちょっと嫌ですね。クールだったりファッショナブルでも良いのですが、音楽よりイメージそのものが好きそうな人達は軽く見えます。何なら音楽じゃない別の畑の人でも、考え方が近い人とは同じインディーロックで括られるバンドよりも話が合うことがありますね。周りのバンドがどうこうというより、自分たちとクリエイティブに対する姿勢が近い人とは今後関わっていきたいとは思いますが、そうじゃなければたとえ同世代で同じタイプの音楽と括られても、わざわざ無理につるんだりはしたくないという気持ちはありますね。不自然なものは嫌いです。
- 自身のジェネレーションに関してどんな印象をお持ちですか? 例えばカルチャーであったりムードだったり…。
- Akiyamaいまはテクノロジーが進みすぎてちょっと人間を超え始めてきてるんじゃないかなと。自分たちよりもインターネットの方が音楽に詳しかったり、そういうなかで情報がすごく氾濫している。情報をとにかく掘って掘ってという人と、情報を完全に掘りきれなくなって、情報から置いていかれる人と2つに別れはじめている気がしますが、ミュージシャンがそのなかでどういう風に自分のクリエイティビティを追ってくのかというのは、いまの子たちにとって大きなチャレンジだと思いますね。80年代、90年代の人たちがどう感じていたのか分からないですけど、いまは10年前のものも、20年前のものも同時にライバルみたいになっていて、新しい曲を出してもそれに似た曲がリアルタイムでインターネット上に同時に存在しているので、「いまそれをやる意味ある?」という問いがいつもある。新しいものを作ることの難しさみたいなものをいまの子たちは余計に感じているんじゃないかなという気はします。
- Kachi流行とかは見え易くなったし、そこにばかり目が行きやすくなったとは思うけど。
- Shimonakaどの時代から何をチョイスしているかみたいな、アーティストのセンスが重視されている気がしていて。「そっから持ってくるんだ、この人たち。センスいいな」とか。でも実際そのものが普遍的なものなのかどうか分からないことが結構多かったり、あとは90年代に比べて見た目も重視されている時代だと思いますね。あとは、いまの世代は諦観が強いなと思うんです。諦観が強いところが一番他の世代と違うのかなと。ムードとしてだらっとした先に進まないムードとか。
- そういう意味で共感するバンドはいますか?
- Shimonaka身の回りはどうかな。
- Akiyamaスタンスも含めていうと海外のバンドともまた違いそうだしな。音的には近くても。
- ShimonakaAkiyamaが実際にどう思っているのか分からないですけど、僕が解釈するには、多分うちのバンドの曲のムードは、バコンって一度希望が全部なくなって真っ暗な状態になって、それでもそこから頑張ろう、前を向こうという姿勢だと思うんです。一度すべての希望がなくなったときに人の本質が表れると思っているなかで、本当に闘おうとしてる人はあんまりいないかなと。いまは何でも上手くできてしまうから。そういう意味で本当にアナログなやり方で現実と当たっていこうとしているアティテュードが合う人はあんまり見当たらない。どこか他のバンドにはみんな達観してカッコつけているところを感じるんで。
- Akiyama確かに“闘う”みたいな部分が抜け落ちているのはあるのかな。音楽って生き方だから、政治に対する姿勢とか哲学的なところとか、音と同じくらいもっとバンドから発信されても良いと思うのですが、みんなかっこよさげな音やクールなファッションしか追ってないというか。LAとかで強く感じたのは、10代のお洒落なキッズ達もライブハウスで政治や国のあり方について酒や音楽やファッションの話と同じレベルでしていて、これは日本じゃなかなか見られない光景だなと。いまの日本のバンドはちょっとイメージばかりを追い過ぎているところを感じることがありますね。もちろん良いバンドもいますし、海外にも中身のないバンドはたくさんいましたが。
- Shimonaka「いや、それは上手くやりすぎ」というのを感じますね。いろんなかっこいい楽器を使ったりとか時代にあってることを上手くやっているけれど…。
- スタイルはそうだけれど。
- Shimonakaそう、スタイルはかっこいいんですけど、アティテュードとして。
- Akiyamaスピリットが抜け落ちてる。
- Shimonaka最近のバンドを観ているとパンクスみたいな闘う気持ちよりもかっこよさで威圧される気がしちゃうんです。「確かにかっこいいけれど、それにぼくはついていけないわ」みたいなところはありますね。
真っ暗な状態から前に進もうとするのが、ぼくらの音楽。

- 個人として影響を受けたアーティストや音楽作品について聞かせて下さい。
- Akiyamaぼくが最初に音楽に入れ込むきっかけになったのはThe ViewとThe StrokesとThe Libertinesでした。結局いろんな音楽を聴きながら最終的に自分の元になっているなというのを改めて感じることが多いです。
- どのあたりに一番シンパシーを感じますか?
- AkiyamaThe LibertinesとThe Viewに関しては初期のパンクと同じように、本当にシンプルなスタイルのまま気持ちを歌っていて、特別上手いことは全然していない。だから自分にもできると思わせてくれたのが大きくて。The Strokesに関してはもう少しアート的なところもあるかもしれません。音楽だけじゃなくて、もっと総合的なイメージが他のバンドには感じない洗練され方でかっこいいなと。そこはジュリアンの感性かなと思うんですけど、ビデオやアートワーク含めひとつの音楽を通して表現していいんだというのが自分のなかではすごく大きな発見だった。David BowieやSex Pistolsなど、アート的な感性で見てもおもしろい人は前からたくさんいたんでしょうけど。
- 世代的に近い方がシンパシーを抱き易いですよね。
- Akiyamaはい。ぼくにとってはジュリアン・カサブランカスが大きな存在でした。
- Kachi高校生のころに出会ったThe Smithsからはかなり影響を受けたと思いますが、彼らのビジュアルや弱点を逆手にとって武器にするようなスタイルは、力強く男らしい、ありふれたロックのイメージに対して当時の自分にはもっとリアルに感じられました。
- Shimonakaぼくはそもそもギターが大好きなので、いろんなギタリストからインスピレーションというか「これいいな」というところを見てきたんです。最近でいうとRadioheadにすごくはまっていて(笑)。ぼくの勝手な想像なんですけど、Radioheadは多分スタジオでものすごく自分たちに挑戦していると思うんです。ああいうストイックでエモーショナルなところを失わないで、実験をして新しい音を出し続けているのはやっぱりすごいですよね。最近、スタジオワークに自分の気持ちが向いてるので、Radioheadの姿勢は尊敬しています。
- Akiyamaあれだけ物作りに徹すると、気持ちが抜け落ちちゃったり曲の良さから離れたりしかねないけどね。
- Shimonakaそのバランス感覚は超すごいなと思っていて。持論ですけど、新しい音を出そうとすると、音が細くて曖昧になってしまうイメージがあるんですよ。エフェクティブにすると芯のないような音がしがちなんですけど、ジョニー・グリーンウッドの新しく出す音はすごい自信で出てきていて。フレーズ自体が革新的というのはもちろんですが、あれを出来たらかっこいいなと思います。あと、ずっとメンバーが変わっていないところも好きです。
- Kamotoぼくは正直DYGLのドラマーとして影響を受けている人はいないですね。DYGL以外でドラムを叩いたことはないし、これからやろうとも思わないんで。
- Akiyamaはっきりしてるね(笑)
- Kamotoだから特に好きなドラマーとかもいないです。
- 個人的にはどうですか?
- Kamoto個人的に言うと、最初に聴いたのがArctic Monkeysだったので、ロックをやるとなるとリバイバル以降の音楽を意識しているのかも知れないです。その前にも洋楽は聴いていたんですが、それこそLINKIN PARKとかGreen Dayだったので。

- 最初の作品はどういう形でリリースされたですか?
- Akiyamaバンドを組んでライブをやり始めの頃は何もないとそのまま終わっちゃうので、観にきてくれた人たちに渡すための、家で作った曲を入れたデモCDを配っていたんです。その後きちんとお金をかけてスタジオに入って作ったのが、もうちょっとデモ音を綺麗にしたバージョンの4曲入りのカセット。一応それがきちんと作った最初の作品でした。あの頃はSoundcloudとかBandcampとかがハシリの時代だったんでネットで上げることが流行っていたし、それも意味があると思ってみんなやっていた。でもそれだけじゃダメなんだと気付き始めているときでしたね。ぼくらにとっても時代全般的にも、そういう流れを感じていました。その後はもうEP(『Don't Know Where It Is』)かな?
- Shimonakaその後はEPだね。
- 名前も途中で変更したり、紆余曲折ありながらもここ一年くらいで急速に実力も意識も変わってきたようにお見受けするのですが、そこには昨年の海外生活や、そこで制作した1st EPでの経験も大きいと思います。この作品が海外での初のクリエイションになると思うのですが、どういう始まりだったんでしょうか?
- Akiyamaさっきの話じゃないですけど、ベースとしては感性や姿勢が近い人と仕事をしたいという想いが常にすごく強くあったので、知り合いの伝手でLAのLolipop Recordsに付随するスタジオで録音するところまで漕ぎ着けたんです。実際録音してみて、やはり欲しい音のコミュニケーションは英語や日本語といった言語的問題に関わらず、音楽的感性によるんだなと。自分たちにとっても新しい経験でした。きちんと海外のスタジオでエンジニアと1枚作品を録れたという経験は、ぼくらにとってもやはりプラスでした。特にあの作品はデジタルじゃなくて完全にアナログなレコーディングだったことも含めて、根本的な音を録るというスタジオワークを肌で経験出来ましたし。
- ジャケットも自分たちで考えられた作品でしたが、そのアートワークもシンプルで素晴らしかったです。パッケージもひとつの作品であると思いますが、どういうポイントを重視していますか?
- AkiyamaあれはLAの練習スタジオで撮ったShimonakaの写真をKachiがデザインし直して完成したアートワークです。ただアイデアはぼくやKamotoも含めみんなでアイディアを出していて、一番イメージに合ったものを選ぼうということであれになりました。
- Shimonakaアイコニックなものと、いままで自分たちが好きだった名盤のジャケットとかに共通する質感があると思うんですけど、それをみんなで探している状態でしたね。だから今回のアルバムもそうですけど、“何かっぽいもの”を真似して間違いが起こらない分、既視感があるものよりも、アイコニックなものになるようには心がけました。
- Akiyama一番は音から感じられるものが反映されているかどうかを大事にしたくて。音とあまりにもかけ離れていたら、たとえいいジャケットでも採用したくない。音にかなりリンクしたものを感じたので、あれを選んだという感じですね。
- それから、7インチ『Waste Of Time』をリリースされましたよね。こちらはThe Avalanchesファンとしてはエンジニアに驚かされました。個人的にはこの作品くらいから音の印象が変わっていて、初期から『Let It Sway』あたりまではアメリカのインディーギターポップ的なサウンドが印象的でしたが、この頃からちょっと英国的というかトラッド的な音に変化してきたように思います。ちょうどearly Beatlesのようなメロディやハーモニーの美しさだとかビートが感じられる。そのあたり何か心境の変化があったのでしょうか?
- Akiyamaそれに関しては結構ぼくも考えることがあるんですけど、多分どの時期もすごく変化はし続けていますね。それこそ3人で始めたばかりのときはメロディもないガレージロックみたいな形だったので、『Let It Sway』くらいまでで随分変化していたんです。そして『Waste Of Time』のあたりでまたさらに変化してきた。それというのは結局ぼくのソングライティングがどんどん自分の趣味にフォーカスされていったというのがあるわけですけど。最初は「ガレージロックを作ろう」という感じでバンドを組んでみたので、そういうものを作ろうと意識していましたが、段々と自然に作れるものを突き詰めるようになった。バンドの形態が4人になった時も変化しましたし、レコーディングやジャケットのことを考えるなかで、自分たちの音が何かというのを考える度に変化していった。多分音楽的な意味では、ぼくのソングライティングに大きく関係している気がします。
- 初期のアメリカのインディーポップらしいサウンドに英国的なサウンドがミックスされたおもしろいサウンドになってきて、DYGLの表現の幅が広がったようにも思いますが、その辺りはいかがですか?
- Akiyamaうれしいですね。最近それも考えることなんですが、それこそPhoenixがフランス出身だったり、Tame Imparaがオーストラリアとか、本当に良いバンドはボーダーを超えてユニバーサルな存在になれると思うので、ぼくらとしても目指すところは、「日本人だから日本語で」とか「日本人だけど英語で歌うのはどうなのか」といった概念をさらに超えていけたらと。もちろん日本人にも受け入れられてほしいし、他の国の人にも受け入れられて欲しいですけど、本当にユニバーサルで普遍的なものを作れたら、それはもうひとつ別のステップにいけるんじゃないかなと思います。英米をわざわざミックスしようという意識は特にないですけど、自分たちのいろんな趣味などが自然に作品として現れているのであれば、それはいいことですよね。
アルバートと仕事をするのは、うれしい反面不安もあり半信半疑でした。
- 影響を受けたであろう事柄を自分のものにどんどん昇華していっている感じがして、頼もしい限りです。そしていよいよフルアルバムがリリースされるわけですが、どうしても話題にされるのは、The Strokesのアルバート・ハモンド Jr.とそのプロデューサーであるガス・オバーグの起用。The Strokesといえば2000年代以降のロックンロールバンドで影響を受けてない人はいないと言っても過言ではないスーパーグループです。彼を起用することになった経緯についても聞かせて下さい。
- Akiyama『Don't Know Where It Is』のレコーディングのときもそうだったんですけど、今回のアルバムをレコーディングするにあたっては、やはり自分たちの音と感性が近い人と仕事をしたいという話がありました。であれば自分たちの好きなアルバムを録った人たちを一回考えてみようという流れで、エンジニアのリストを作っていたんですけど、そのなかにガスの名前があって。他にも何人かいたからその人たちにアプローチしてみようというときに、別の縁もあってガスが日本人のバンドと仕事をしたがっているというお話が耳に入ったんです。
- Shimonaka仕事したがっていたのはアルバートじゃなかったっけ?
- Akiyamaガスとアルバートか。
- Shimonaka二人セットで。
- Akiyamaガスの名前はこちらでもリストにあげているし、その話をよくよく聞いてみたらガスだけではなく、どうやらアルバートと二人でプロデュースしたいという話で。
- 最高じゃないですか。
- Akiyamaはい。でもすごくうれしかった反面、ぼくらの前に彼らが最近手掛けたThe Viewの5枚目のアルバムは、、本当にアルバートの作品のようになっていたので、彼と仕事をすることによってぼくらの作品もアルバートそのものになってしまったら逆にこわいなという話はしていましたね。ガス一人と働くのは無理かも聞いてみたんですけど、「二人じゃないと動けない」と言われて。最初はうれしい反面不安もあり、半信半疑でした。
- 最初からプロデューサーは入れる方針ではなかった?
- Kachiもともとはエンジニアのみの予定でした。
- Akiyamaなので、なおさらプロデューサーとしてアルバートが来ることで自分たちの意見の純度が下がるのはこわいな、というのはありました。
- Shimonakaこれまでの他のバンドのように、ぼくらより有名なアルバートの名前が世に出ていくことを恐れている面もありましたし。まあ作品自体が良くなったので、いまとなっては全然いいんですけど。
- Akiyama終的には作品が良ければ。実際自分たち4人とも影響を受けているバンドのメンバーだし、それ以上の話が他にある感じもしなかったので、それだったら一歩踏み出して二人に賭けるのもいいんじゃないかなと。
- やってみていかがでしたか?
- Akiyama仕事は素晴らしかったです。とてもおもしろかった。自分たちが影響を受けてきた人に自分たちの曲を聴いてもらって、それが良いか悪いか判断してもらえるというのもとても不思議な体験でした。
- まずは曲のやりとりから始まったのでしょうか?
- Akiyama一番大事なのは曲ということで、アルバートもそこを最も気にしていました。レコーディングは9日間だったんですが、その2日間前に「ベルリン」というNYのバーをアルバートが貸し切ってくれて、曲の確認会みたいなことをやったんです。そこで、ぼくらが用意した自分たちの曲をひたすら演奏して、アルバートがメモを取って「この曲はこうした方が良い」というやりとりを2日間やって、レコーディングに入るという形でした。最も自分たちの励みになったのは、アルバートが自分たちの曲をすごく気に入ってくれたこと。そもそも仕事を何で受けてくれたのかをレコーディングの後に聞いてみた時も、「曲が良かったから受けたし、良くなかったら絶対に受けなかった」とはっきり言ってくれて。レコーディング中も、ことあるごとに彼らが良いと思ったポイントは指摘してくれて励みになりました。その分ダメだと思う点もハッキリ言ってくれましたけど。いざやってみて音楽に対して、「これはいる、これはいらない」という判断が物凄くハッキリしていたし、しかも速い。自分たちでアレンジが終わっていない曲に関してもすごく的確なアドバイスを必ずくれました。それでもたまにわけのわからないアドバイスもあったりしたんですけど(笑)。そういうときはぼくらが意見したら、それもきちんとリスペクトして聞いてくれました。互いが本当に「これが良いね」というところまで何回も試させてくれたんです。
- 一番影響を受けた部分というのは? 何か新しい発見はありましたか?
- Kachiプロデューサーが付くこと自体初めてだったから、録音前に第三者と楽曲の内容について話し合ったことはとても新鮮でした。なかでもアルバートは曲の構成をなるべくタイトにしようとしていたのを感じました。
- Shimonakaよりミニマルにしようと。
- シンプルに、ということですよね。個人的に一番感動したのは、グルーブというかバンド感が以前の作品と比べて全然違う点です。The Beatles然りPhonix然り、バンドとしてバランスが良いグループに魅力を感じる自分としては、リズム隊はリズム隊で最高だし、ボーカルは楽器としても魅力的で最高に官能的だし、ギターは的確というか迷いがなくて、かなりオラオラしてるというか…(笑)。
- Shimonakaオラオラしてますね、これは(笑)。
- その辺りはプロデューサーの力も大きいのかと思いました。
- Kachiそうですね。プロデューサーも含め、今回は期間が限られていたから一発録りで初めて録音したことも大きかったと思います。
- 録音の手法が違ったということですか?
- Kachiそうですね。それが結果的にすごく良く作用したなと個人的には感じていますね。
- Akiyama10日で14曲だから、そうしないと絶対に間に合わなかった。
- Kachiあとは、いつもよりレコーディングまでの準備に時間を掛けられたということかな。
- Shimonaka準備はあったね。

- オープニングの『Come Together』は完全にThe Strokesを彷彿とさせるロックンロールですが、この曲について教えて下さい。
- Akiyamaこの曲がいつ頃出来たかはハッキリ覚えてないんですけど、わりと最近出来た曲です。たしか前々回にNY行った頃だったかな。最初は強調されたビートに対してメロディのない、かなりポスト•パンクな曲だったんです。けれど、それもさっき話した曲作りの変遷とリンクするところがあって、曲をまとめていけばいく程メロディもしっかり立ってきて、バンド感もまとまってきた。きっとそれがいまのDYGLらしさだと思います。メロディが生まれ始めてからのサウンドはもう少しアンビエントな印象で、サイケ寄りのシューゲイズをイメージしていたんです。けど、レコーディングの過程でアルバートと話しながら自分たちに一番合う形に曲をまとめていくなかで、どんどんタイトにミニマルにという感じになりました。
- 中盤のギターが個性的で最高ですよね。
- Shimonakaあれは、実はアルバートと揉めてるんです。ぼくはエフェクトを増やしたくて何回もアルバートに「エフェクト足していい?」と聞いたら、「絶対ダメ。絶対ダメ」って(笑)。
- Akiyama実際にこの曲は至るところで揉めました。イントロも違う感じで考えていたのを、バコっと取られてしまって。長いことぼくは納得いってなかったので、何回か突っかかったんですけど(笑)。でも曲全体の構成だったりサウンドの質感だったりを確かめていくなかで、それはそれで曲として形になったなと最後には満足しました。
- Shimonaka「彼が正しかった」とぼくのなかで納得しているので。またひとつ勉強になりました。
- この曲は歌詞においても、今作を作る上で感じたものすべてを集約した内容になっている気がしますが、どんなことをフォーカスしたかったんですか?
- Akiyama自分としては、他の曲はもう少し普遍的なテーマを曲の質感に合わせて落とし込みたいというのがチャレンジだったんですけど、この曲はあえて2017年に自分が音楽を作っている意味を見出してみたいなと考えていました。さっきも言った通り、いまは情報が過多になって人々がいろいろなことを見失ったり、気にしなくてもいいことのせいで気が散ったり、物事がどんどん浅くなっている。それは自分を戒める意味でも感じていることではあるのですが、結局自分たちはいまどこにいるんだろうと。David Bowieが死ぬ前に『Where Are We Now?』という曲を歌っていましたが、それに近いことをテーマにしてみたかった。これはある程度テーマを事前に頭のなかに思い描きながら書いてみたんです。で、結局いま自分がどこにいるかとかどこに向かってるかということは答えとしてハッキリしている訳ではないですが、自分たちにはとにかく前に進むことしかできない。
- それがアルバム全体のテーマになっているのかなと。全編を読んで感じたのは、いまの時代を象徴している内容であること、またとてもモダンで、サウンドの熱に比べるとどこか冷めたものを感じたこと。もがいているというよりは、諦めながら新時代を進んでいるみたいな印象を受けました。
- Akiyama諦観だ(笑)。でも自分としてはそれをエネルギーにして闘うことも大事だし、エネルギーになる曲だという印象で捉えています。本当に諦めている曲に諦めている歌詞を書いたら落ち込んじゃうので、そういうのは嫌ですね。
- 歌詞に反してサウンドが熱いから、バランスがいいのかとも感じました。アルバム一枚がいまのみなさんのポートレートだと思うのですが、全体的には何を考えましたか?
- Akiyamaコンセプト•アルバムとテーマを明確に決めている場合以外は、最終的にはアルバムとは曲ごとのテーマだと思っています。フォトアルバムにいろんな写真が入っている状態が自分のいまの気分なので。「アルバムの答えはこれだよ」とひとつの答えを提示するのが個人的には嫌で、聴く人や時々の気分で見えるものが異なるアルバムが一番良い。でもひとつは、さっきShimonakaが話していたように、自分たちにも困難なことや見えないことがありながらも前に進む力が音楽には欲しいと思っています。それは極論では自分のためなんですけど。自分がその音楽を書いて、自分自身の気持ちを確かめたいというところがぼくの出発点なんです。曲を書くことは楽しい。それを通してぼくが前に進みたい。だからこそ聴く人にもそういうエネルギーを感じてもらえたら嬉しいですね。

- そんな気持ちも込めてネーミングされているのだと思いますが、アルバムタイトルの意味を聞かせて下さい。
- Akiyamaこれは『Take It Away』という曲の一節から取りました。歌詞、言葉は全部ぼくが書いているから、タイトルも基本的に自分がまずアイデア出そうと決めています。いくつか案を考えていて、それこそ1枚目だから『DYGL』というセルフタイトルはどうか、何かの曲名を使おうかとか考えたんですけど、出してみた案のなかで最も詩的に響くと感じたのがこのタイトル。始めから「このタイトルじゃなきゃダメだ」というわけではなかったんですが、最終的に響きや意味を含めてこのタイトルを選びました。“Say Goodbye”は別れの言葉なのでネガティブな響きもありますけど、きっとそのときに感じていたのはこの言葉にある“過去に決別する力強さ”で、ぼくとしてはそれが前に進む力になれば良いなと。そういう意味で『Come Together』のテーマと同じかもしれません。「Memory Denとは何か?」ということは全員に聞かれることなんですが、“Den”という言葉には“在りか”とか“住処”、“場所”、“巣”という意味があって、自分が読んできた詩のなかで使われていたり、響きが好きだったので頭の片隅にあったんじゃないかな。もともとは歌詞に使えれば良いなと考えていたのですが、最終的にはこの一節がタイトルにふさわしいと思いました。
- その言葉は聴く人とか、見る人に詩的な余白を残していますよね。
- Akiyama余白は残したいですね。「こういう答えです」とは言い切りたくないので、気に入っています。
- Shimonakaあとアルバム全体として、Akiyamaが作る曲には軽やかな部分とちょっと暗い部分があるんです。“Say Goodbye”というところで軽く、“Memory Den”というところでちょっと重いという両性具有的なところもぼくは彼に合っていると思っているので、このタイトルは好きですね。
- リアルというものがあるとして、常に絶妙なバランスでそれを感じさせてくれて、個人的には本当にワクワクしています。インディとメジャー、インポートとドメスティックというボーダーが関係ない、超越した世界でしなやかに活躍していくのを応援しています。ありがとうございました。
- 一同ありがとうございました。