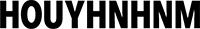Girls Just Want To Have Fun!

写真家・永瀬沙世さんの作品世界には共通する静けさがある。
それは宇宙空間を漂うスペース・シャトルの中のような、深いプールに潜ったときのような。
2006年に発表した写真集『青の時間』から2016年の『CUT-OUT』までの10年間、
モチーフや手法を変え、実験を重ねながらいまも永瀬さんは“何か”の気配を探っている。
今回は新作『THE VOID』を展示した個展と写真集の発表に合わせて、
アートディレクションを担当したYOSHIROTTENさんをゲストに迎えた
対談(だったりそうじゃなかったりする)インタビューをお届けします。

ミラクルを信じて、宝箱を開けるように創造する。
- まず最初に、永瀬さんが写真を始めたときのことを教えてください。
- 永瀬沙世(以下永瀬):15歳くらいのときに「いま頭の中にある世界を何かで表そう」と思って、音楽をやったり、映像を作ったり、文章、グラフィック、演技もやってみたんです。その中で一番自分の感覚と身体にカチッとあっていたのが写真だったんです。入り口が広いというか、一般の人が日常に使っているものなんだけど、それを極めている人とそうでない人との差が大きいものは何なんだろうと思って。音楽や映像は関わる人が多すぎるなぁと当時感じていて、とっても人に気を使ってしまうところがあるので、そこにエネルギーを注ぎ込むと純度が鈍っていくんですよ。だから、最初から最後まで一人で完結できるのって写真とか文章で、さらに機械を通すってことは自意識になりすぎず、すごくパブリックだなって思ったの。それで一番おもしろいなと思ったのが写真だったんです。だから色々試した挙句の果てなんですよ。いまもおもしろいから、その頃と変わってない。
- 今回の作品『THE VOID』は、スナップ写真のコンタクトシートに写っている女性の脚を、顕微鏡のレンズで撮影したシリーズです。まずどういうところからコンセプトを考えるんですか?
- 永瀬:特別なきっかけはいつもなくて、常に探しながら5つくらいの作品を3年くらいかけて同時進行でやってるの。コンセプトはそんなに簡単に思いつかなくて、むしろ最初から頭でコンセプトが見えたものは自分の域を超えていないから、納得がいかないものになる。それを自分で打ち消して、作りながらポロって溢れてきたアイデアを膨らませてっていうのを繰り返していく。だから、いつも何ができるか分からなくて、空中に漂っているものを掴んで地に下ろしての繰り返しをしているようなイメージなんです。

- 今回は顕微鏡を使っているのが面白いですね。
- 永瀬:そう! もともとスナップを撮るのが好きで、海外に行ったときもよく撮るんですけど、人間がうじゃうじゃいる写真のなかの、米粒より小さい人たちを顕微鏡で拡大して撮っていくんです。最初はフィルムで撮ってからベタ焼きにして、それを顕微鏡を通してデジタルで撮る。フィルムとデジタルを両方使っているし、間に顕微鏡も入っている。しかもその前には引き伸ばし機を挟んだりといくつもの行程を経ているからすごくぼやけてくるし、いろんな粒子が出てくるんです。
- 不思議な感じです。前作は切り絵で今回は顕微鏡ですが、こういう実験的な手法はどうやって見つけるんですか?
- 永瀬:日々の「やってみたいな~」とか「楽しいな~」とか、そういうアンテナを人生で死守していて。今回は顕微鏡か望遠鏡を使ってみたいなと思っていて。切り絵のときは遊びから始まって、それが作品になった。そもそも日常を何も予想してないから、宝箱のような感じで…。最終的な絵はいつも見えてないんです。普通は見通しを立てて進むと思うけど、それだと可能性が狭まる気がしちゃう。私の場合は、ミラクルを信じてるんです。

写真家・永瀬沙世とアートディレクター・YOSHIROTTENの出会い。
- 前作『CUT-OUT』に続いて今作でもYOSHIROTTENさんがアートディレクションを担当しています。二人の出会いは?
- YOSHIROTTEN:僕がとある女性シンガーのCDジャケットをディレクションしていて、ジャケットの写真を沙世さんにオファーしたのが最初です。もともと作品が好きでよく見ていたんですけど、こんなにポヨポヨしている人だとは思わなかった(笑)。もっとシャキっとした強そうな方かなって。
- 永瀬:ウエストポーチ! カメラマンベスト! みたいな?(笑)
- YOSHIROTTEN:そう、ジーパン! みたいな(笑)。そんな印象を持っていたら、初めて恵比寿の喫茶店で打ち合わせをしたときにすごくポヨポヨ~っとしていたので、それからサヨポヨって呼んでます。
- 永瀬:その日は紺色のスカートを履いてたから、キャリアウーマンっぽくシュッと見えてると思ってた。初めての仕事だからかっこつけて行ったつもりなんだけどな~。

- 作家としてはお互いどう感じていますか?
- YOSHIROTTEN:作家としての沙世さんは、コマーシャルな仕事をしているというよりは、作品を発表しているとか、海外から写真集を出しているという印象が強かった。やっぱり、光の捉え方が独特で、ずっと彼女の写真は見ていました。一緒に撮影をしたときもすごくいい写真で、しかも現場も楽しくて。
- 永瀬:私は、何の前情報もなく会ったから、「ミュージシャンの人が来た!」と思った(笑)。『CUT-OUT』を一緒にやり始めたのは、『SPRITE』の前まで自分がストイックになり過ぎていたからなんです。他者を挟みこまないような作品の作り方をしていたんですけど、ちょっと濃度が濃すぎたので、これは第三者が入ってほしいなって思うようになって。自分だけで対話をする世界はもうやりきって、誰かを信頼できる余裕ができてきた。それで『SPRITE』をアートディレクターの米山菜津子さんと一緒にやったらすごく良かったんですよね。でも、まだ自分の中でどこか背負っているところがあって。もっと身軽になってアクセルを踏み込むにはどうするか思ったときに、ちょうど背負ってくれそうな人を見つけた(笑)。私は直感だけで生きてるから、感覚とロジカルの両方の感覚を絶妙なバランスで持っているという稀有な才能のYOSHIROTTENさんとなら、ぴったりはまるという確信があったんだと思う。

- 今回の写真集はどんなやり取りを経てできあがっていったんですか。
- 永瀬: 最初から展示と写真集という二軸で考えていて、展示ではいろいろなバリエーションの写真を計200枚くらい使って、写真集は真逆のミニマムな世界にしたかった。タイトルの『THE VOID』っていう単語が、真空とか無、空洞みたいな意味で、なんかぎゅっとした、でも空っぽなイメージがあったから。とにかく純度を上げたかったから、1000カットくらいあるなかから極限まで写真を絞りました。その作業が一番難しかった。酸素も音もない、宇宙のような“無”にしたかった。ちなみに、VOIDと呼ばれる何もない場所が実際に宇宙にあって、その形が顕微鏡で撮って、そのまま使った表紙の写真にとっても似ているんですよ。
- YOSHIROTTEN:最初に見たときは、これってすごく“宇宙”らしいなと思った。いっぱい送られてくるサムネイルをひとつのフォルダに入れて見ていると、青の滲みとか黒のぼやけた感じが、80年代より前の、月面着陸の写真集のザラつきと色味が似てるなって。
- 永瀬:父が宇宙関係の仕事をしていたから、「宇宙飛行士とかかっこいいな~」と思っていて。写真家もそうだけど、女性が男性の職業をやるのが子供の頃かっこいいと感じていたんです。そういう憧れが刷り込まれて、その頃のイメージがずっと残ってる。空を見上げるのも好きで、月とか宇宙とか地球とか、大きいものが好き。一緒だよね?
- YOSHIROTTEN:うん、よくNASAとかの話もしてたよね。無音っていうイメージはいま初めて聞いたけど、写真を見て同じように感じてた。
- 永瀬:素の状態というか、本質を追求した見せかったの。写真をこれだけ絞ったのもそうだし、いかに研ぎ澄まして本質に入れるかっていうのをいつも探してる。でも、いざ写真集が完成するとすぐ変わりたくなるから、そう思っていた私はもうここにはいないんだけど(笑)。

ものづくりにおいて、二人が大切にしてきたこと。
- いまの10代、20代の人たちは、発信しやすい時代ということもあって「自分で何かを作りたい」という人が増えていると思うんです。ものを作るということに対して、大事にしていることはなんですか?
- YOSHIROTTEN:僕は、とにかくたくさん作ってきたという自負があります。10代の頃も会社に入っていたときも、休みの日や仕事終わった後の数時間を使って自分の好きなものをずーっと作ってた。作ってみないと分からないことがたくさんあるから。そういう時間を経てようやく、どれがかっこいいとか微妙だとかそういうのが分かってくる。数をこなすことによって選択ができるようになったんだと思う。それだけで世界が変わります。
- 永瀬:まさにそうだね。ゴールが見えないのが当たり前で、常に実験してる。人生、実験だなぁと思います。成功する前提で動くんじゃなくて、目の前のものに夢中になった結果、こういうものができている。だから、作品に対してロジカルになるときと、夢中になる時間を同時にしない方がいい。一度夢中で作ってみてから、名前を考えたりして余白をなくしていく。右脳と左脳を使い分ける感じです。

- すぐに自分の作品を世のなかに発信できるようになった反面、誰かの下について勉強する“下積み期間”を経ずに創作活動をしている人も多いじゃないですか? お二人はそれについて、ご自身の過去を振り返ってどう思いますか?
- YOSHIROTTEN:何を目標にするかによって変わると思うんですけど、いろんなことをやりたいなら多くの経験をした方がいいと思います。例えば、デザイン会社に入って図面を勉強して現場を見て、レイアウトを何百パターンもやる生活をすれば、何かしら身につくものがある。ただ、若いときの衝動で作るものはもっと新しい“何か”を生むかもしれないので、結局のところ両方やった方がいいと思います(笑)。いまはいろんな発表の手段があるから、そんな時代にそれを使わず我慢しているより、どんどんやったほうがいい。でも、テクニックは誰かに教わっていくものだと思うから、そういう技術と衝動がミックスできれば最強なんじゃないかな。
- 永瀬:たしかに! 私が10代20代のときは、若さゆえの衝動で進んでしまうと、3つくらいの引き出ししか持てなくてすぐ空っぽになっちゃうと思ってた。というか、その先にあるクリエイティブな豊かさや深さという本当のおもしろさに気付くまえにくじけてしまう気がして。だから逆算して、みんながきらめく20代前半に地味なトレーニングや研究や制作をコツコツとやっていたかな。それがあるからいまがあると思うし、若いときにストイックにやって型を作っていた分、あとは年を重ねるごとにどんどん枠を外して自由になるだけ。自分のやり方を追求していって、自分を信頼して心を開放するだけかな。